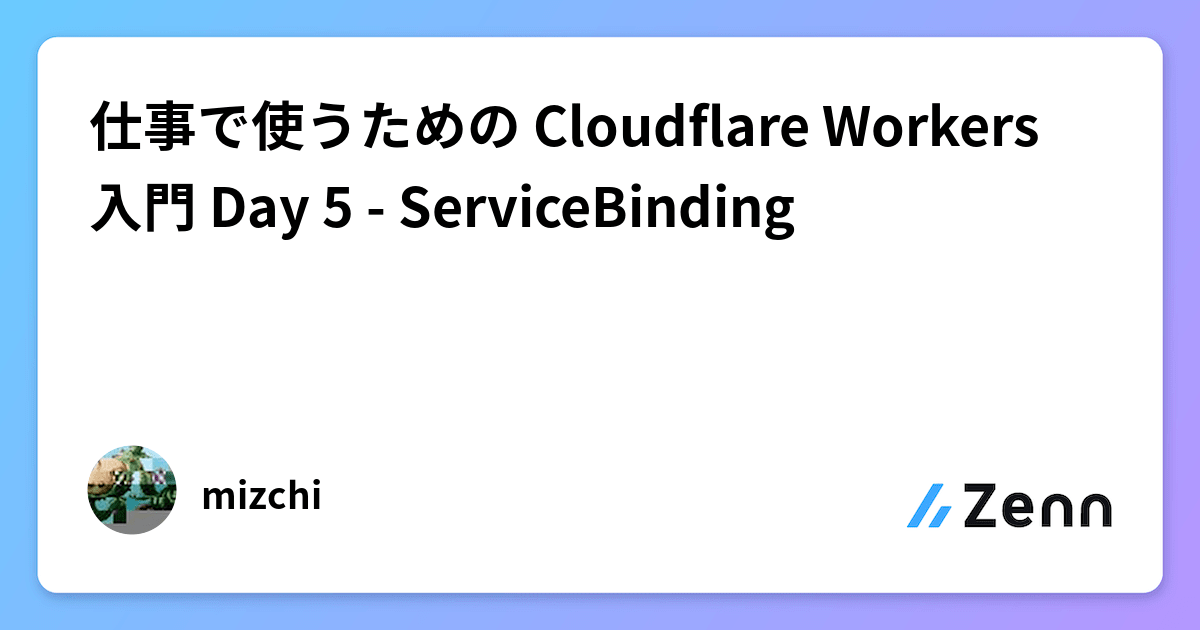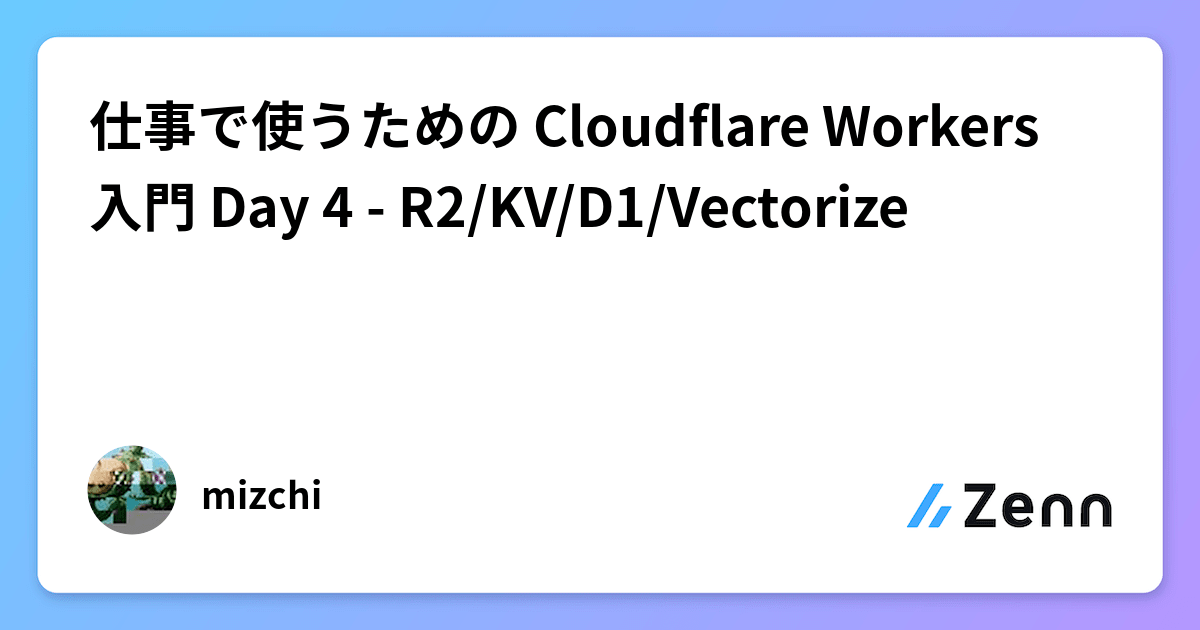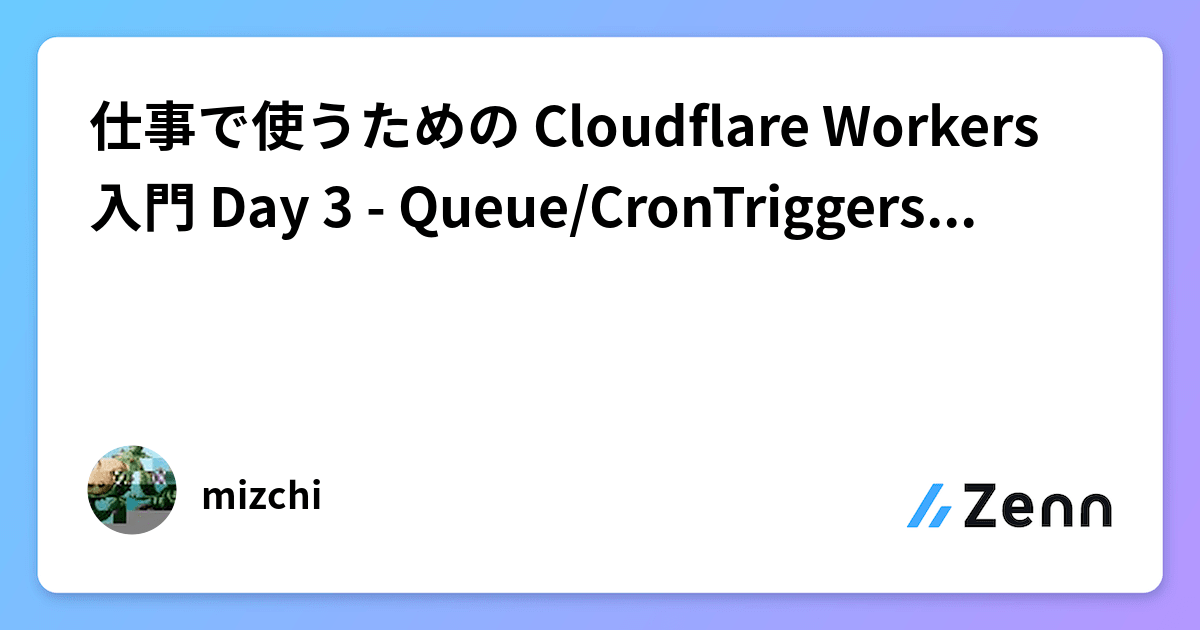この記事では、bitとbit-relayを使用したP2Pコラボレーション開発ツールの紹介が行われている。bitはGit互換のCLIツールで、bit-relayはP2P中継サーバーを介してGitHubを経由せずにリポジトリのクローンやプッシュを行うことができる。bitはissueやPRのストレージを内蔵しており、GitHubに依存せずにこれらを管理できる。具体的な使い方として、リポジトリの作成、issueの作成、リレーサーバーを介した共有方法が示されている。また、bitとbit-relayの利点として、分散型のissue/PR管理や、NAT/ファイアウォール越しのリポジトリ共有が挙げられている。最終的には、P2Pで開発されたものをGitHubに同期することが想定されている。 • bitはGit互換のCLIツールで、e2eテストを通過している。 • bit-relayはP2P中継サーバーを介してGitHubを経由せずに操作が可能。 • bitはissueとPRのストレージを内蔵し、中央サーバーに依存しない管理ができる。 • リレーサーバーを使用することで、NATやファイアウォール越しにリポジトリを共有できる。 • 分散型のissue/PR管理が可能で、特定のホスティングに依存しない。
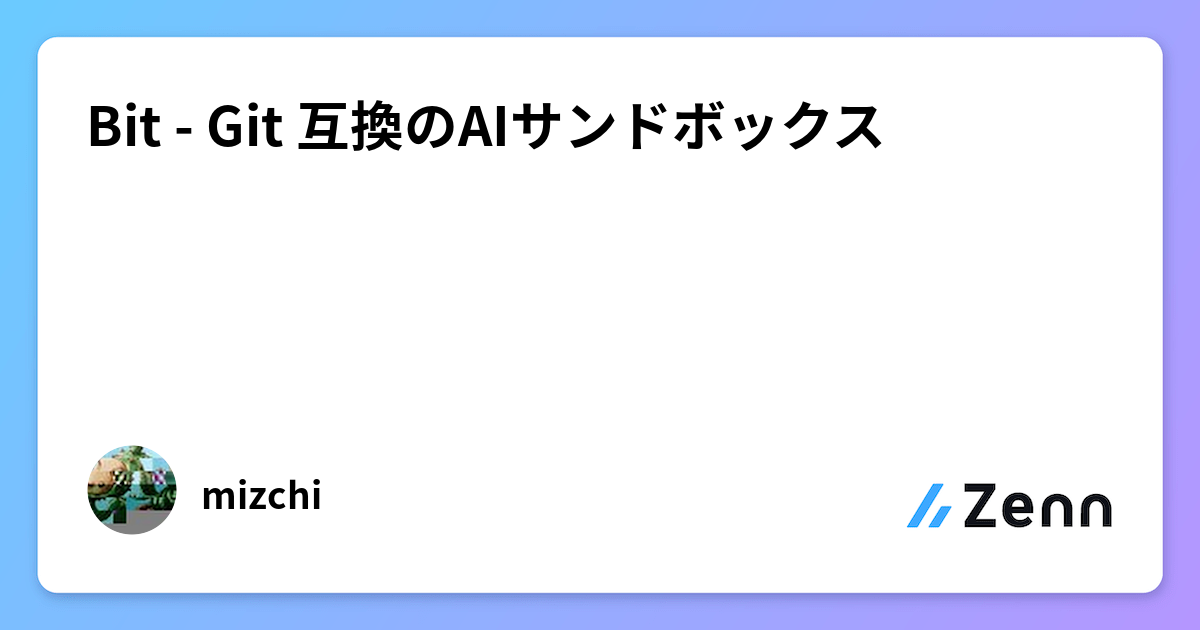
この記事では、Git互換のAIサンドボックス「Bit」の実装について説明されています。Bitは、Gitの拡張機能を持ち、特に特定のサブディレクトリだけをクローンして双方向にプッシュする機能を提供します。インタラクティブなコマンドやGPG署名などの一部機能は未実装ですが、Git本体のテストケースを97.6%通過しています。また、AIエージェントが利用できるサンドボックス環境を提供するために、Gitのオブジェクトをファイルシステムのバックエンドとして使用する仮想ファイルシステムや、P2Pノード間でのGitオブジェクトの共有を想定したKVストアなどの実験的機能も紹介されています。最終的には、AIによる自動マージ機能の実装も視野に入れています。 • Git互換のAIサンドボックス「Bit」を実装した • 特定のサブディレクトリだけをクローンして双方向にプッシュする機能を持つ • インタラクティブなコマンドやGPG署名は未実装 • Git本体のテストケースを97.6%通過 • AIエージェント用のサンドボックス環境を提供 • Gitオブジェクトをファイルシステムのバックエンドとして使用する仮想ファイルシステムを実装 • P2Pノード間でのGitオブジェクトの共有を想定したKVストアを実装 • AIによる自動マージ機能の実装を計画中

この記事では、自作のブラウザMoonBitのレイアウトエンジンを構築する過程が詳述されています。主にCSSのボックスモデル、Flex、Gridの座標計算モジュールを実装し、HTML/CSSパーサやCSSクエリエンジンも一部実装しました。実装の参考として、Yoga Layout EngineやRust製のTaffyを調査し、最終的には自作のエンジンをスクラッチで書くことを選択しました。Web Platform Tests (WPT)を通過することを目標に、テストケースを通じてブラウザの互換性を確保するための努力が強調されています。また、Double Dirty Bitを用いたパフォーマンスチューニングや、CSS: Containの有用性についても言及されています。 • 自作ブラウザMoonBitのレイアウトエンジンを構築した • CSSのボックスモデル、Flex、Gridの座標計算を実装 • Yoga Layout EngineやTaffyを参考にした • Web Platform Tests (WPT)を通過することを目指した • Double Dirty Bitを用いたパフォーマンスチューニングを行った • CSS: Containの有用性を実装過程で確認した

この記事では、WebAssembly Component Modelのライブラリをwa.devに公開したことについて説明しています。wa.devはWebAssembly Component Modelのパッケージレジストリで、言語に依存せず型安全な相互運用を可能にします。具体的には、シンタックスハイライト用のレンダラーライブラリ「mizchi:tmgrammar」を公開し、トークン配列をHTMLまたはANSIエスケープシーケンスに変換する機能を持っています。ライブラリはwkgを使用して取得でき、wasmtimeで実行可能です。また、JavaScriptから利用するためのバインディング生成方法も紹介されています。 • wa.devはWebAssembly Component Modelのパッケージレジストリである。 • シンタックスハイライト用のライブラリ「mizchi:tmgrammar」を公開した。 • ライブラリはトークン配列をHTMLまたはANSIエスケープシーケンスに変換する。 • wkgを使用してライブラリを取得し、wasmtimeで実行できる。 • JavaScriptから利用するためのバインディング生成方法がある。

この記事では、Viteを使用してMoonbitでフロントエンドを開発するためのプラグイン「vite-plugin-moonbit」について説明しています。このプラグインは、Moonbitを使った開発を簡素化し、ホットリロード機能を提供します。開発者は、Moonbitの設定が難しいと感じることが多いため、簡単に始められる環境を整えることが目的です。具体的には、MoonbitのビルドプロセスをViteに統合し、開発中のコードを自動的にリロードする機能を実装しています。記事では、インストール手順や基本的な使用方法、サンプルプロジェクトのリンクも提供されています。さらに、WASMを使用した例や、外部パッケージの利用方法についても触れています。 • Moonbitをフロントエンドで使う際の設定の難しさを解消するためのプラグインを開発した。 • ViteとMoonbitのビルドプロセスを統合し、ホットリロード機能を実現した。 • インストール手順や基本的な設定方法を示し、簡単に始められる環境を提供している。 • サンプルプロジェクトとして、MarkdownコンパイルやWASMライブラリの読み込み例を用意している。 • 外部パッケージの利用方法や、Luna UIフレームワークとの統合についても説明している。

Moonbit Advent Calendarの振り返りでは、Moonbitというプログラミング言語の普及を目指し、参加者を集めることに成功したことが述べられています。最初は軽いリファレンス記事を考えていましたが、他の参加者の熱意に触発され、より深い内容の記事を書くことになりました。特に、Moonbitの実利やパフォーマンスを示すことに重点を置き、実際に何かを作ることやベンチマークでの優位性を証明する記事が好評でした。また、Moonbitの機能として、演算子のオーバーロードやパターンマッチングが強力であることが強調されています。最終的に、Moonbitを使ったさまざまなプロジェクトや実装例が紹介され、言語の魅力が伝えられています。 • Moonbitの普及を目指したAdvent Calendarの成功 • 参加者の熱意に触発され、深い内容の記事を作成 • 実利やパフォーマンスを示すことが重要 • 実際に何かを作ることが好評 • Moonbitの演算子オーバーロードやパターンマッチングの強力さ • さまざまなプロジェクトや実装例の紹介

Luna UIは、軽量で高速な宣言的UIライブラリで、WebComponentsを基盤にしたSSR(サーバーサイドレンダリング)をサポートしています。著者は既存のUIライブラリに不満を持ち、自らのニーズに応じたライブラリを開発しました。Lunaは、Signalによる細粒度のリアクティビティを提供し、コンパイル時の最適化が不要なほど小型です。サンプルコードを通じて、Lunaの使い方やその軽量性が示されており、Reactと比較してもバンドルサイズが小さいことが強調されています。また、Viteとの統合を容易にするためのプラグインも開発されており、エラーレポート機能も備えています。デモとして、シューティングゲームやTodoMVCが紹介され、Lunaのパフォーマンスが実証されています。 • Luna UIは軽量で高速な宣言的UIライブラリである。 • WebComponentsを基盤にしたSSRをサポートしている。 • Signalによる細粒度のリアクティビティを提供する。 • Reactと比較してバンドルサイズが小さく、実装が簡単である。 • Viteとの統合を容易にするプラグインを開発した。 • デモとしてシューティングゲームやTodoMVCがあり、パフォーマンスが実証されている。

Moonbitのmoonコマンドには、型チェックやバックエンド指定実行、ドキュメントテスト、スナップショットテスト、型定義生成、メソッド検索、ベンチマーク、カバレッジ分析などの便利な機能が備わっています。特に、moon lintによる型チェックとlintの統合、moon runによるターゲット指定実行、moon testによるドキュメントとテストの統合が強調されています。これにより、未使用の変数や型引数に対する警告が出力され、CI環境でのエラー管理が容易になります。また、moon docコマンドを使用することで、型のメソッド一覧を簡単に確認でき、標準ライブラリのソースを読むことなく機能を理解できます。 • moonコマンドには型チェック、バックエンド指定実行、ドキュメントテストなどの機能がある • moon lintによる型チェックとlintが統合されている • moon runコマンドでターゲットを指定してプログラムを実行できる • moon testでドキュメントとテストを統合し、サンプルコードの陳腐化を防ぐ • moon docコマンドで型のメソッド一覧を確認できる • moon benchでベンチマークを実行できる • moon coverage analyzeでテストカバレッジレポートを取得できる
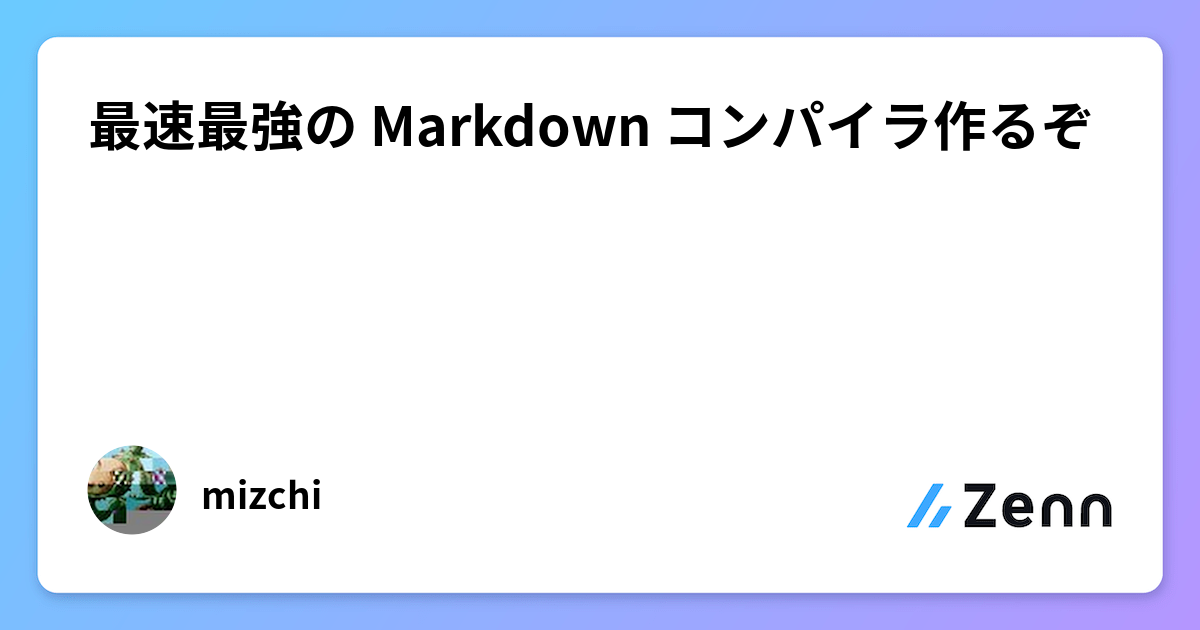
この記事では、最速のMarkdownコンパイラを実装したことについて述べています。特に、インクリメンタルコンパイルに焦点を当て、20000文字のテキストでも60fpsを維持できる性能を実現しています。Moonbitという言語を使用し、FFIを使わないピュアな実装で、js/wasm/native環境で利用可能です。CommonMark準拠は微妙ですが、GitHub Flavored Markdownの拡張に対応しています。CST(Concrete Syntax Tree)を採用し、差分更新を効率的に行うことで、パフォーマンスを向上させています。最終的に、他の実装と比較しても優れた速度を示しています。 • インクリメンタルコンパイルにより、編集時のパフォーマンスが向上する。 • CSTを使用して、ユーザーの入力に対して効率的に再パースを行う。 • CommonMark準拠は207/542で、実用上問題ないと判断。 • GitHub Flavored Markdownの拡張に対応している。 • 他のMarkdown実装と比較して、速度が優れている。

この記事では、Moonbitを使用してlibgit2のバインディングを作成する方法について説明しています。まず、MoonbitのNativeバックエンドを利用し、libgit2のC APIを呼び出すための基本的なNative FFIの解説が行われます。次に、簡単なC関数をMoonbitから呼び出す方法を示し、その後、実際のlibgit2ライブラリのバインディング実装に進みます。libgit2はGitの機能を提供するCライブラリであり、リポジトリの操作やコミット履歴の取得などが可能です。記事では、動的ライブラリのロード、メモリ管理、エラーハンドリングなどの課題に対処する方法も詳述されています。最終的に、MoonbitからGitリポジトリを操作できるようになることが目指されています。 • Moonbitを使用してlibgit2のバインディングを作成する方法を解説 • Native FFIの基本的な仕組みを理解する • libgit2を利用したリポジトリの操作が可能になる • 動的ライブラリのロードやメモリ管理、エラーハンドリングの課題に対処 • 簡単なC関数をMoonbitから呼び出す実装例を示す

この記事では、Moonbitのパッケージレジストリであるmooncakes.ioについて紹介しています。mooncakes.ioは、rubygemsやcrates.io、PyPIのようなパッケージレジストリであり、Moonbitに関連するライブラリを提供しています。Moonbitのライブラリは、Pure Moonbitの実装でどこでも動作するものと、特定のバックエンドで動作するものに大別されます。具体的には、標準ライブラリのmoonbitlang/coreや、非同期処理を扱うmoonbitlang/async、実験的な準標準ライブラリのmoonbitlang/xなどが紹介されています。また、サードパーティライブラリの使用方法や、プロジェクト生成、依存関係の追加、ビルド方法についても詳しく説明されています。最後に、コア開発者によるライブラリの利用を推奨しています。 • Mooncakes.ioはMoonbitのパッケージレジストリである。 • ライブラリはPure Moonbitの実装と特定バックエンド用に分類される。 • moonbitlang/coreは標準ライブラリで、暗黙に読み込まれる。 • moonbitlang/asyncは非同期処理のためのライブラリで、イベントループを実装している。 • moonbitlang/xは実験的な準標準ライブラリで、json5やcryptoなどが含まれる。 • サードパーティライブラリの追加方法やプロジェクト生成の手順が説明されている。 • コア開発者のライブラリを中心に使用することが推奨されている。

この記事では、Node.jsとReactを利用するためのMoonbitのJSバインディング集であるmizchi/js.mbtについて説明しています。Moonbitを使用することで、TypeScriptの代わりにJavaScriptのブリッジコードを書くことなく、Node.jsやReactを利用できるようになります。具体的には、JSビルトインへのバインディングや、Node.jsへのバインディング、よく使われるnpmパッケージへのバインディングを提供し、TypeScriptの表現力を補完することを目指しています。また、実装手順として、ReactとCloudflare Workerが動作するバインディングを最初に作成し、その後Web標準の仕様を参考にAPIを整備しています。最終的には、Moonbitを使ったプログラミングが可能になることを目指しています。 • Node.jsやReactを利用するためのMoonbitのJSバインディング集を作成している。 • Moonbitを使うことで、TypeScriptの代わりにJavaScriptのブリッジコードを書く必要がなくなる。 • JSビルトインやNode.js、npmパッケージへのバインディングを提供し、TypeScriptの表現力を補完する。 • 実装手順として、ReactとCloudflare Workerが動作するバインディングを最初に作成し、APIを整備している。 • Moonbitを使ったプログラミングが可能になることを目指している。

MoonBitは、moon newが生成するテンプレートに関する技術的なディスカッションを提供します。記事では、MoonBitの機能や利点、使用方法について詳しく説明されています。特に、テンプレートのカスタマイズや拡張性に焦点を当て、開発者がどのようにこれを活用できるかを示しています。また、MoonBitを使用することで得られる効率性や生産性の向上についても言及されています。全体として、MoonBitは開発者にとって有用なツールであり、特にテンプレート生成において強力な選択肢となることが強調されています。 • MoonBitはmoon newが生成するテンプレートに関する技術的なディスカッションを提供する。 • テンプレートのカスタマイズや拡張性に焦点を当てている。 • 開発者がMoonBitを活用する方法を示している。 • MoonBitを使用することで得られる効率性や生産性の向上について言及されている。 • MoonBitは開発者にとって有用なツールである。

この記事では、Moonbitというプログラミング言語におけるJavaScript FFI(Foreign Function Interface)の実装方法について解説しています。Moonbitはまだ発展途上の言語であり、ライブラリが不足しているため、FFIを通じてJavaScriptとの連携を強化することが重要とされています。具体的には、MoonbitからJavaScriptのAPIを呼び出すための手法や、ビルド設定、型定義の生成方法について詳しく説明しています。また、実際にReactのMoonbitバインディングを作成する過程で得た知見も共有されています。最終的には、Moonbitを用いたクロスプラットフォーム運用を目指すことが理想とされています。 • Moonbitはアーリーステージの言語で、ライブラリが不足している。 • JavaScriptとの連携を強化するためにFFIの実装が重要。 • MoonbitはJSだけでなく、nativeやwasmのコードも生成可能。 • FFIを通じてJavaScriptのAPIを呼び出す手法を解説。 • ビルド設定や型定義の生成方法について具体的な手順を示す。 • ReactのMoonbitバインディング作成の過程で得た知見を共有。 • 将来的にはMoonbitの純粋な実装に寄せていくことが理想。

MoonBitは、TypeScriptの不安定さやRustの低レベルさに対する不満を解消する新しいプログラミング言語です。2025年11月時点での進化として、ネイティブバックエンド対応、組み込みJSON型、例外処理、非同期処理が追加され、実用性が向上しています。著者はMoonBitを使用してReactのバインディングを作成し、SPAとして動作させることに成功しました。言語の特徴として、Rust風の構文、パターンマッチ、明示的な副作用制御、代数的データ型、組み込みのテストランナーなどが挙げられ、特に生成コードのサイズが小さいことが利点とされています。公式の学習リソースやドキュメントも提供されており、開発者がMoonBitを学ぶためのサポートが整っています。 • MoonBitはTypeScriptの不安定さとRustの低レベルさを解消する言語。 • 2025年11月時点でネイティブバックエンド、組み込みJSON型、例外処理、非同期処理が追加。 • 著者はMoonBitを使ってReactのバインディングを作成し、SPAとして動作させた。 • Rust風の構文、パターンマッチ、明示的な副作用制御、代数的データ型をサポート。 • 生成コードのサイズが小さく、npmにライブラリを公開するのが現実的。 • 公式の学習リソースやドキュメントが提供されている。

この記事では、Moonbitを使用してReactアプリを開発する方法について説明しています。著者は、Moonbitを使ったシングルページアプリケーション(SPA)の実装に取り組み、Reactプログラマにとって自然に感じられるAPIを目指しています。具体的なコード例として、カウンター機能を持つコンポーネントが示されており、テストも@testing-library/reactを用いて行われています。MoonbitはJavaScriptバックエンドを持ち、Reactとのバインディングを実装するために、DOMやEcmaScriptのビルトインオブジェクトへのバインディングを行っています。著者は、必要な機能を優先して実装したライブラリを一つのパッケージとして管理しており、今後の拡張も考えています。 • Moonbitを使用してReactアプリを開発する方法を解説 • カウンター機能を持つコンポーネントのコード例を提供 • @testing-library/reactを用いたテストの実装 • JavaScriptバックエンドとReactのバインディングを実装 • 必要な機能を優先して実装したライブラリを一つのパッケージで管理

この記事では、Moonbitの現在のステータスとOpenAI APIを利用するためのコードの実装方法について説明しています。Moonbitは現在ベータ版で、2026年に1.0のリリースが予定されています。最近の変更により、Moonbitはjs/native/wasmのクロスプラットフォーム言語としての方向性が強まっています。OpenAI APIを利用するためのコードをCLIで実行し、HTTPリクエストを送信してJSONをパースする手順が示されています。具体的には、環境変数の取得、HTTPリクエストの送信、JSONのパースといった機能を持つライブラリを使用して、実用的なコードを構築する方法が解説されています。 • Moonbitは現在ベータ版で、2026年に1.0を予定している。 • Moonbitはjs/native/wasmのクロスプラットフォーム言語としての方向性が強まっている。 • OpenAI APIを利用するためのコードをCLIで実行する手順が示されている。 • 環境変数の取得、HTTPリクエストの送信、JSONのパースを行うライブラリを使用している。 • 具体的なコード例が提供されており、実用的なアプリケーションの構築が可能。

この記事では、OpenAIのCodexを使用してプロジェクト固有のMCP(Model Context Protocol)を設定する方法について説明しています。CodexはグローバルにMCPを設定することしかできないため、プロジェクトごとに独立した設定が必要です。2つの手段が提案されており、1つ目は環境変数を使用して読み込みディレクトリを変更し、プロジェクト固有の設定をロードする方法です。しかし、この方法では認証情報が含まれるため、普段使いには適していません。2つ目の手段は、Codexのコマンドラインオプションを使用して直接TOML設定をロードする方法で、こちらの方が安全です。具体的なコマンドや設定例も示されており、実装に関する注意点も記載されています。 • CodexはグローバルにMCPを設定するが、プロジェクトごとに独立した設定が必要な場合がある。 • 手段1では環境変数を使用してプロジェクト固有のMCP設定をロードできるが、認証情報が含まれるため普段使いには不向き。 • 手段2では--configオプションを使用して直接TOMLをロードする方法があり、こちらが安全とされる。 • 具体的なコマンドや設定例が示されており、実装方法が詳細に説明されている。 • JSONからTOMLへの変換に関する注意点も記載されている。

この記事では、ボックスモデルの視覚的な差分を自動的に検出するツール「visc」を紹介しています。このツールは、指定されたURLをクロールし、DOMのBoundingRectを抽出して、視覚的なボックスモデルの差分を計測します。具体的には、ヒューリスティックなアルゴリズムを用いて、視覚的に近い要素を比較し、SVG形式で差分を出力します。開発者は、手動でのE2Eテストを避けつつ、CSSやJSの変更によるレイアウト崩れを迅速に検知できるようになります。CLIを通じて、複数のビューポートでのテストが可能で、初回実行時には自動キャリブレーションが行われます。 • 視覚的なボックスモデルの差分を自動的に検出するツール「visc」を開発した。 • 指定されたURLをクロールし、DOMのBoundingRectを抽出して比較する。 • ヒューリスティックなアルゴリズムを用いて、視覚的に近い要素を検出し、SVG形式で差分を出力する。 • 手動でのE2Eテストを避け、CSSやJSの変更によるレイアウト崩れを迅速に検知できる。 • CLIを通じて、複数のビューポートでのテストが可能で、初回実行時には自動キャリブレーションが行われる。

この記事では、AI技術を用いたopencodeとkimi-k2の使用について説明しています。著者は、Claude-codeの調子が悪いため、opencodeとkimi-k2を試すことにしました。SWE-bench Verifiedでのスコアは65.8%で、Gemini 2.5 ProやClaude 4 Sonnetと比較しても高い水準です。kimi-k2のAPI利用料は非常に安価で、出力トークン価格は1Mあたり$2.50と設定されています。設定方法についても詳しく説明されており、openrouterのAPIキーを取得し、opencodeをインストールして設定する手順が記載されています。最終的に、ツールも動作するようになり、著者は使用感についても言及しています。 • Claude-codeの調子が悪いため、opencodeとkimi-k2を試した。 • SWE-bench Verifiedでのスコアは65.8%で、Gemini 2.5 ProやClaude 4 Sonnetと比較して高い。 • kimi-k2のAPI利用料は1Mあたり$2.50と非常に安価。 • openrouterのAPIキーを取得し、opencodeをインストールして設定する手順が説明されている。 • 設定後、ツールも動作するようになったが、日本語入力に問題がある。
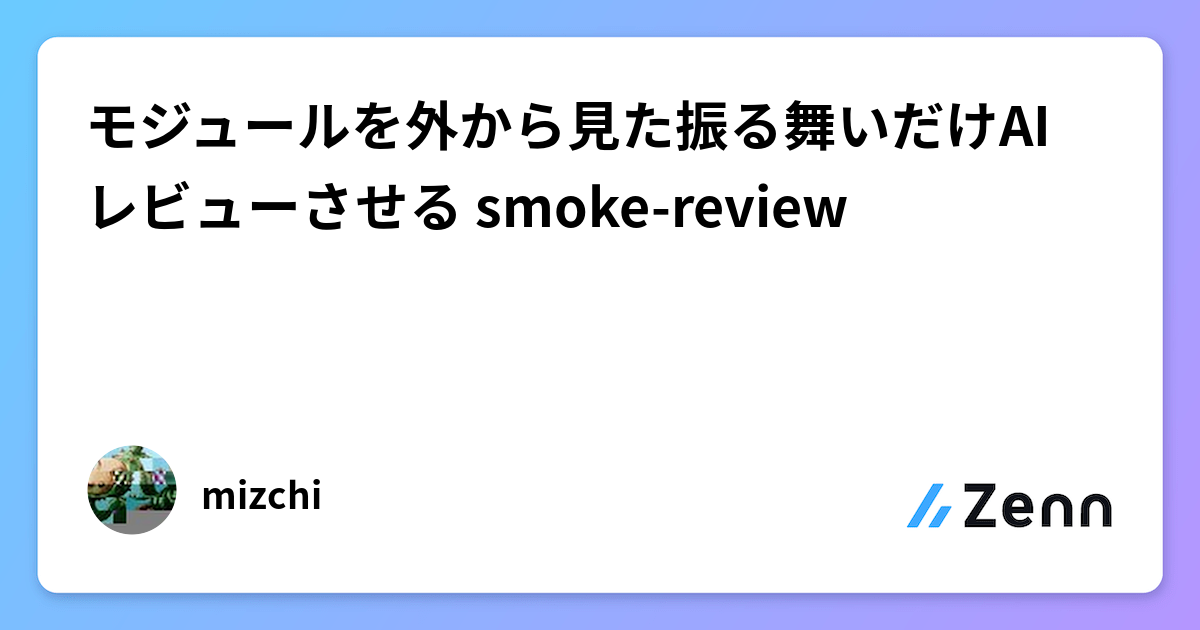
この記事では、AIを活用したコードレビュー手法「smoke-review」について説明しています。具体的には、モジュールの外部からの振る舞いをAIにレビューさせることで、実装者バイアスを排除し、効率的なレビューを目指しています。Claude Codeにおいて、5時間のレートリミットが導入されることを受けて、コンテキスト消費を抑えるためのテクニックが実装されました。具体的には、公開APIとテストケースをAIにレビューさせるための設定が行われ、レビュータスクを並列で処理する方法が提案されています。また、型定義を利用してライブラリの使い方を確認するアプローチも紹介されています。 • AIを用いたコードレビュー手法「smoke-review」の導入 • 実装者バイアスを排除するためのアプローチ • 公開APIとテストケースをAIにレビューさせる設定 • レビュータスクを並列で処理する方法の提案 • 型定義を利用したライブラリの使い方確認の重要性

この記事では、DiscordからClaude Codeを操作するための一時的なサーバーを構築する方法について説明しています。基本的には、ホストマシンでサーバーを起動し、出先で簡単に操作できることを想定しています。最初にDiscordのトークン、サーバーID、チャンネルIDを取得する必要があります。サーバーが起動すると、Discord BOTがスレッドを作成し、ユーザーの入力を監視します。ユーザーの入力はclaude-code SDKを通じてClaude Codeに送信され、その結果がDiscordに出力されます。注意点として、個人用のDiscordチャンネルでの使用を推奨しており、公開チャンネルでの使用は避けるべきです。実装はDenoスクリプトに含まれており、改造も可能です。 • DiscordからClaude Codeを操作するための一時的なサーバーを構築する方法を説明 • Discordのトークン、サーバーID、チャンネルIDを取得する必要がある • サーバー起動後、Discord BOTがスレッドを作成し、ユーザー入力を監視 • ユーザー入力はclaude-code SDKを通じてClaude Codeに送信され、結果がDiscordに出力される • 個人用のDiscordチャンネルでの使用を推奨し、公開チャンネルでの使用は避けるべき • 実装はDenoスクリプトに含まれており、改造が可能
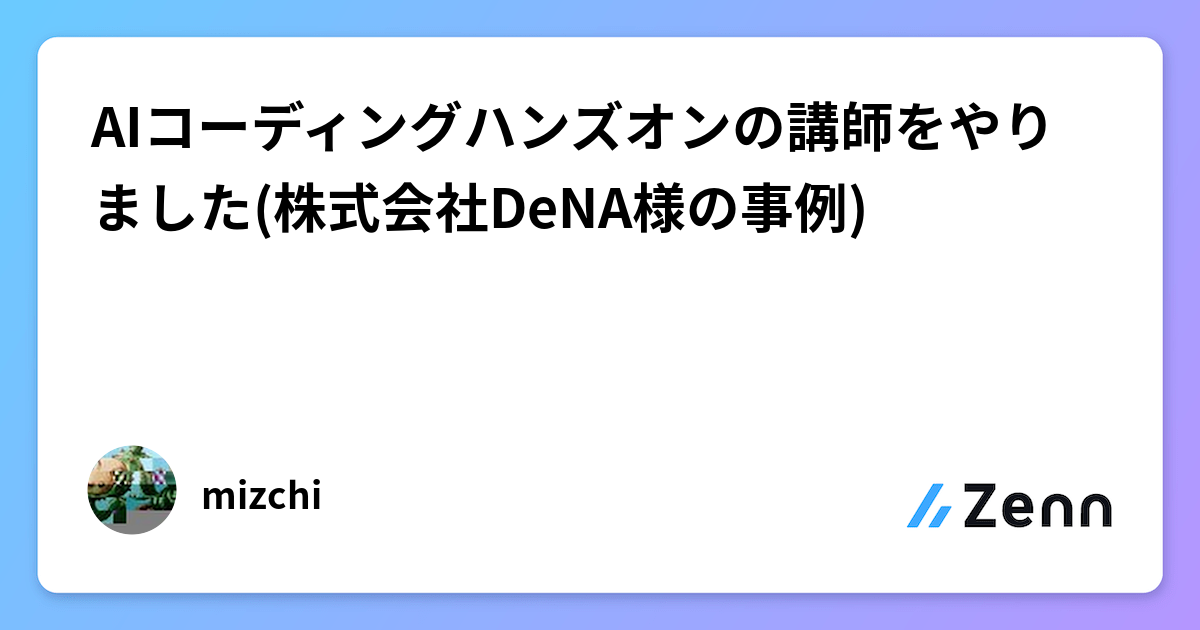
この記事では、株式会社DeNAでのAIコーディングの社内勉強会の講師を務めた経験について述べています。著者は、AIを活用したプログラミングの講師として、受講者に伝えたいことや講師としての心構えをまとめています。事前準備として、作例のリポジトリを用意しつつも、受講者がゼロからプロンプティングする体験を重視しています。また、当日の進行方法や教材の準備、受講者の期待値コントロールについても触れています。特に、AIの環境構築の難しさや、実際のデモを通じて受講者に体験してもらうことの重要性が強調されています。最後に、勉強会の規模や課題についても言及し、今後の依頼については相談が必要であると述べています。 • AIコーディングの講師としての経験を共有 • 受講者にゼロからプロンプティングする体験を重視 • 事前準備として作例のリポジトリを用意 • 当日の進行方法や教材の準備についての考慮 • AIの環境構築の難しさを体感させる • 受講者の期待値コントロールの重要性 • 勉強会の規模や課題についての言及

この記事では、Unison言語についての学習ログが記録されています。Unisonは、従来のプログラミング言語とは異なるワークフローを要求し、純粋関数型とエフェクトシステムを持つ新しいプログラミング言語です。Unisonの特徴として、すべての関数が自己参照ハッシュで表現され、Gitに相当する機能が組み込まれています。Unison Code Manager(UCM)を使用することで、コードの変更を管理し、型チェックとバージョン管理が統合されています。インストール方法や基本的な使い方も説明されており、VSCode拡張を利用してプロジェクトを作成し、簡単なコードを実行する手順が示されています。 • Unisonは従来のプログラミング言語とは異なるワークフローを要求する。 • すべての関数は自己参照ハッシュで表現され、Gitに相当する機能が組み込まれている。 • Unison Code Manager(UCM)を使用してコードの変更を管理し、型チェックとバージョン管理が統合されている。 • インストールはHomebrewを使用するのが簡単で、VSCode拡張も利用可能。 • Unisonでは、純粋関数のテスト結果がキャッシュされる。
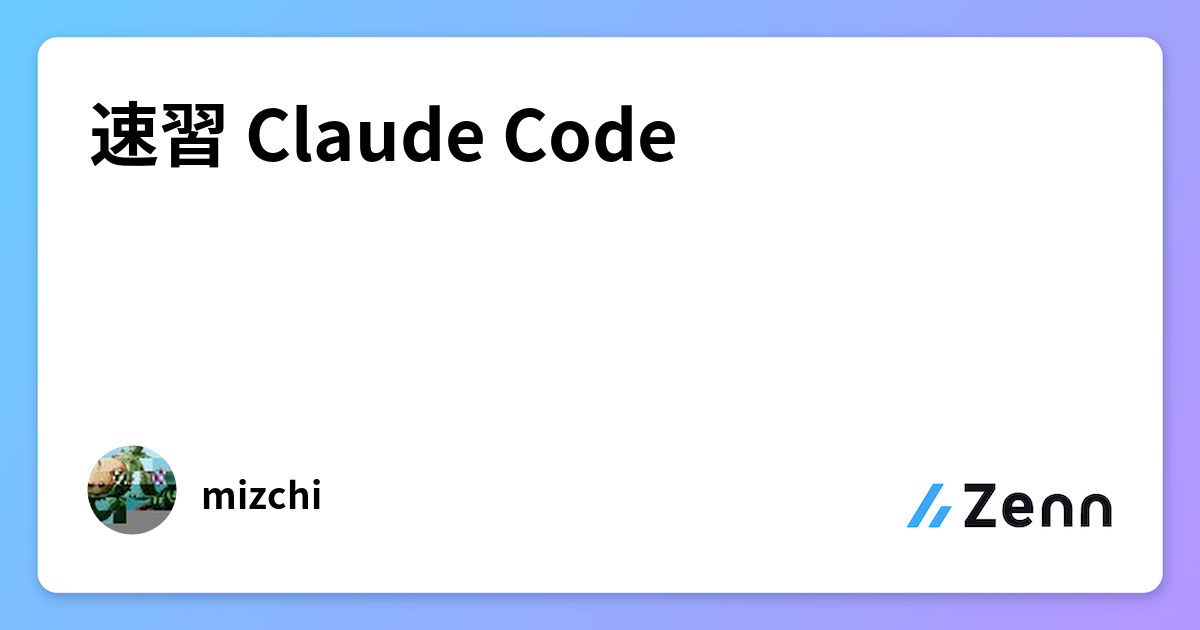
この記事は、Claude Code AIの速習ガイドであり、主にインストール方法や基本的な使い方、セッション管理、コマンドの実行方法について説明しています。まず、npmを使用してClaude Codeをインストールし、簡単なコマンドでAIと対話を開始できます。セッションの管理方法として、直近のセッションに戻る方法や、会話履歴をリセットするコマンドが紹介されています。また、セキュリティ設定やカスタムコマンドの作成方法も触れられており、ユーザーが自分のニーズに合わせてAIの動作を調整できるようになっています。最後に、レートリミットについての注意点も記載されています。 • Claude Codeのインストール方法はnpmを使用する • セッション管理の基本的なコマンドが紹介されている • セキュリティ設定は.jsonファイルで行う • カスタムコマンドを作成することで機能を拡張できる • レートリミットに関する注意点が記載されている
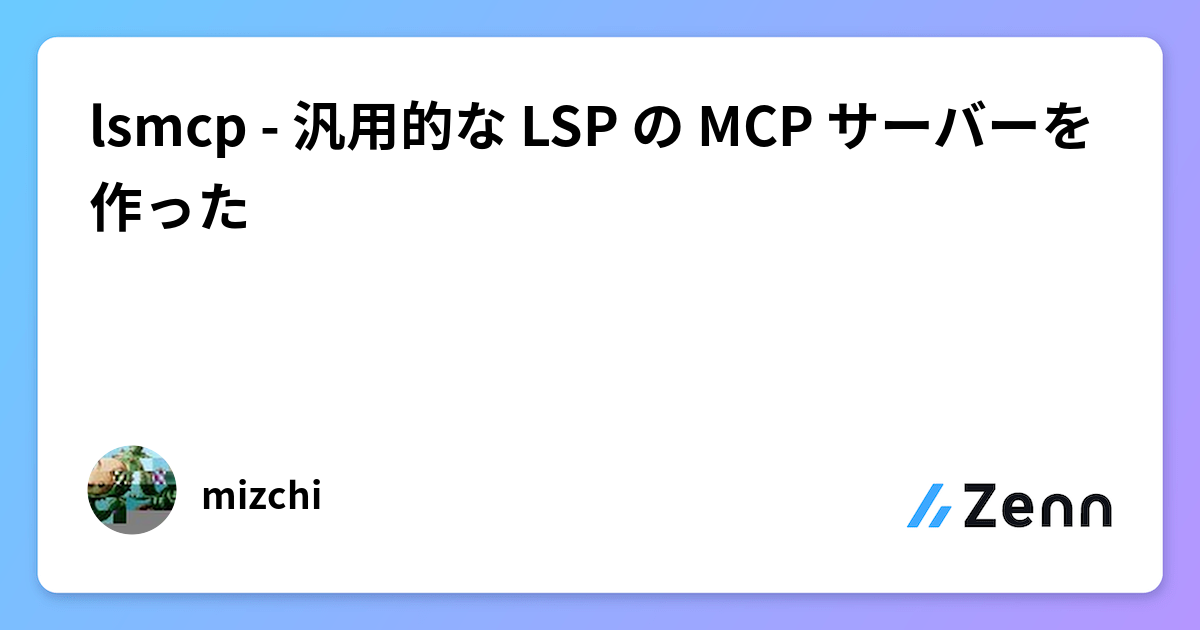
この記事では、汎用的なLSP(Language Server Protocol)を使用したMCP(Multi-Channel Protocol)サーバー「lsmcp」の開発について説明しています。前回はTypeScriptに特化したMCPサーバーを作成しましたが、今回はRust、Python、Goなど任意の言語に対応できるように一般化しました。LSPプロセスを起動することで、リネームやオートインポートなどの操作が可能になります。具体的な使用方法として、各言語のサーバーをインストールし、プロジェクト固有の設定を行うことが推奨されています。主な機能には、定義へのジャンプ、参照検索、シンボルのリネーム、コードフォーマットなどが含まれます。今後の展望として、AIがコードベースを理解し、効率的にタスクを実行できるようにするための試行錯誤が必要であることが述べられています。 • 汎用的なLSPを使用したMCPサーバー「lsmcp」を開発した。 • Rust、Python、Goなど任意の言語に対応可能。 • LSPプロセスを起動することで、リネームやオートインポートなどの操作が可能。 • 各言語のサーバーをインストールし、プロジェクト固有の設定を行うことが推奨される。 • 主な機能には、定義へのジャンプ、参照検索、シンボルのリネーム、コードフォーマットなどがある。 • AIがコードベースを理解し、効率的にタスクを実行できるようにするための試行錯誤が必要。
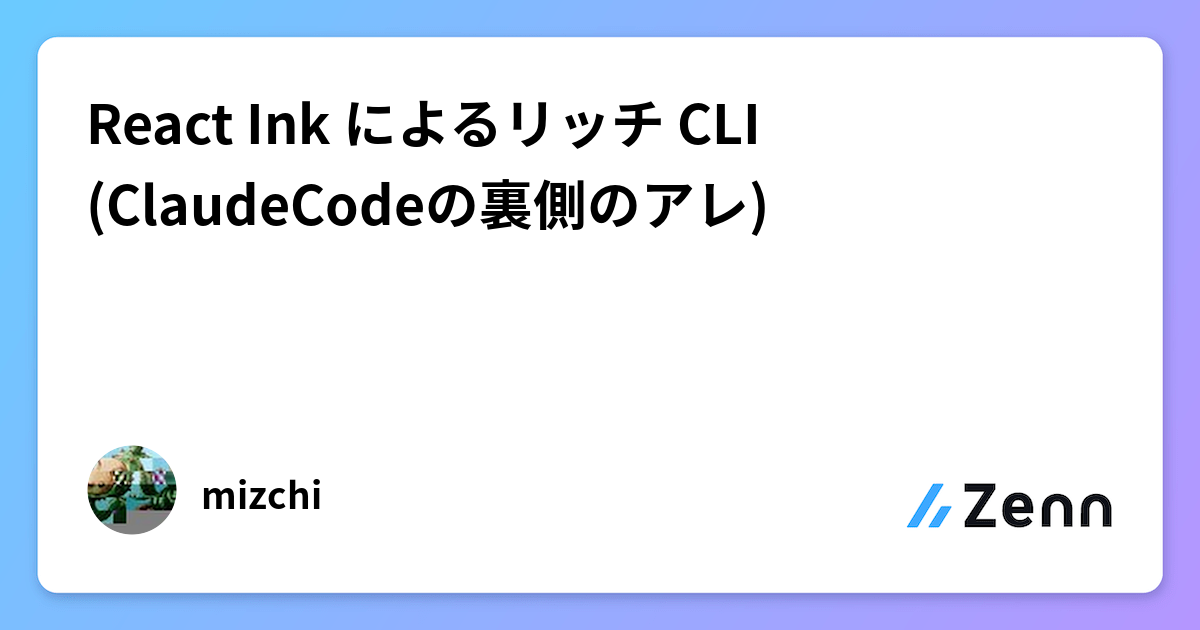
この記事では、React Inkを使用してリッチなCLI(コマンドラインインターフェース)を構築する方法について説明しています。React Inkは、Reactのカスタムレンダラーを利用してCLIを作成するためのライブラリで、内部でYogaというレイアウトエンジンを使用しています。これにより、ReactやReact Nativeの知識を活かしてCLIのUIを構築できます。具体的な実装例として、ターミナルで動作するゲームが紹介されており、自動進行のバトルシステムやインベントリ管理などの機能が実装されています。また、React Inkは多くの有名なライブラリでも使用されており、CLIの開発がAIとの相性が良い理由についても言及されています。 • React InkはCLIを構築するためのReactのカスタムレンダラーである。 • Yogaレイアウトエンジンを使用しており、React Nativeと同様のレイアウト計算モデルを持つ。 • ターミナルで動作するゲームの実装例があり、自動進行のバトルシステムやインベントリ管理機能が含まれている。 • Reactの知識を活かしてCLIのアスキーアートUIを作成できる。 • CLIはAIとの相性が良く、テキストベースのインターフェースは自動化が容易である。
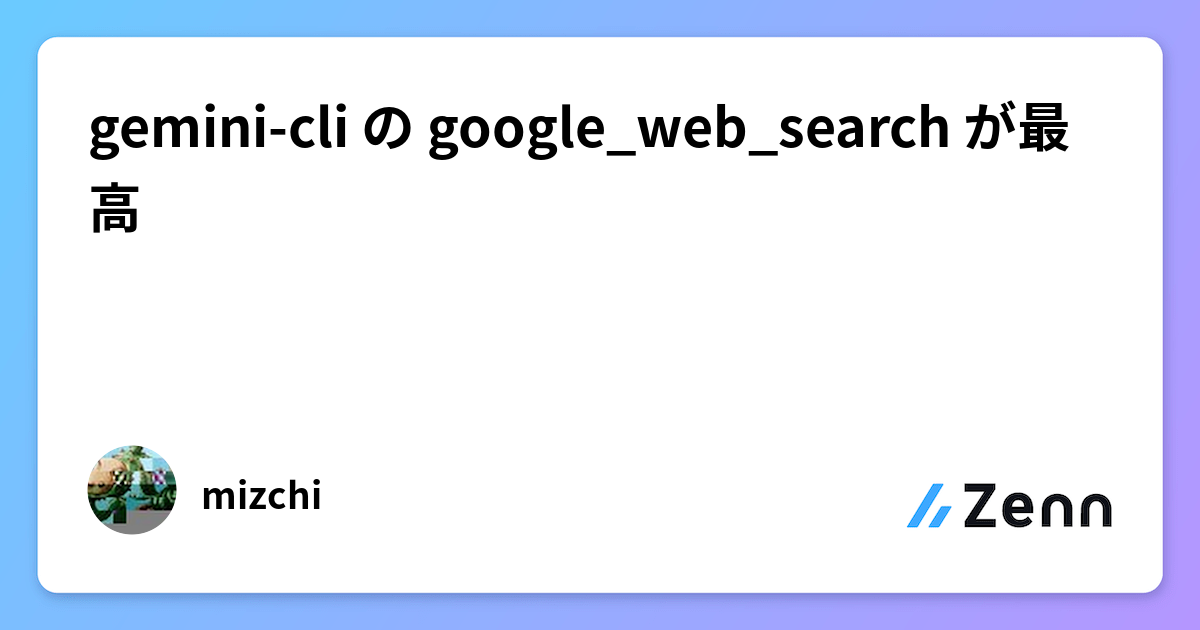
この記事では、gemini-cliのgoogle_web_search機能について説明しています。gemini-cliは、Googleのアカウントに接続することで、Web検索を行うことができるツールです。特に、gemini-cliは、claude-codeの検索機能が貧弱であることを補うために設計されており、使いやすいGoogleの検索結果を提供します。初期化フローやセットアップ方法も紹介されており、npmを使用してインストールする手順が示されています。また、Gemini APIの料金体系についても触れられており、入力トークン数や出力トークン数に基づく従量課金制が説明されています。 • gemini-cliはGoogleのアカウントに接続してWeb検索を行うツールである。 • gemini-cliのgoogle_web_search機能は、claude-codeの検索機能を補完する。 • セットアップはnpmを使用して行い、初期化フローが提供されている。 • Gemini APIの料金は、入力トークン数、出力トークン数、キャッシュされたトークン数に基づく従量課金制である。 • Googleの検索結果を利用できるため、使いやすさが向上している。
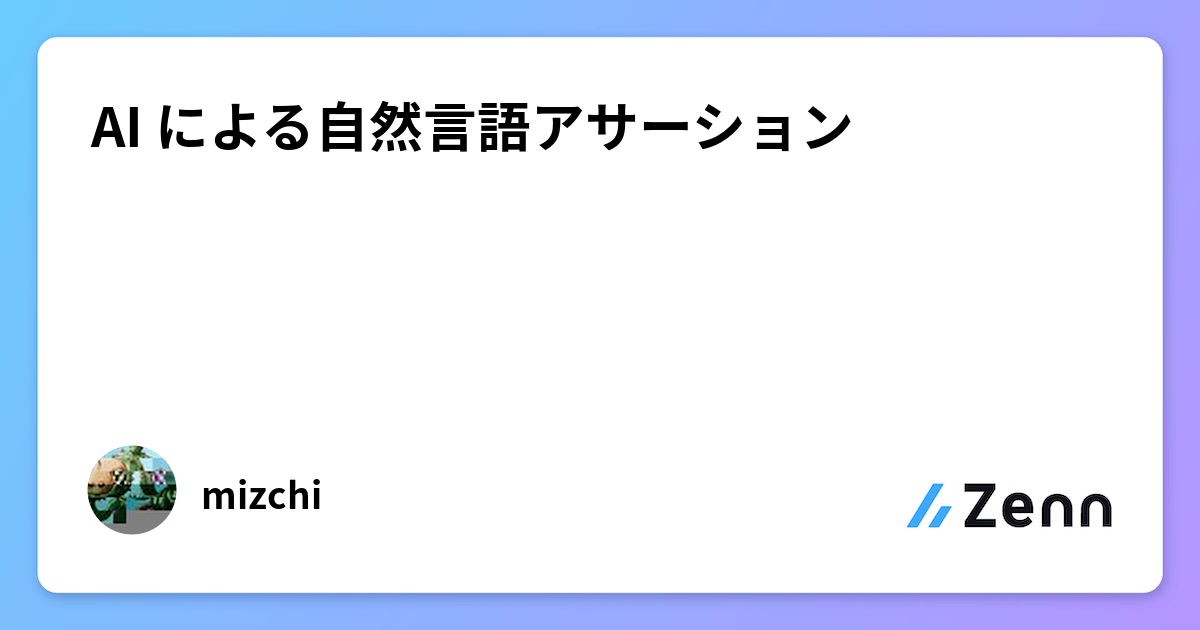
この記事では、AI Claude Code SDKを使用して、TypeScriptやPythonコードから自然言語によるアサーションを行う方法について説明しています。具体的には、テスト中にAIを利用して条件を満たすかどうかを確認するアイデアが紹介されています。コード例として、`assertAI`関数が示されており、特定のプロンプトに基づいてAIが応答する仕組みが解説されています。この方法では、AIが条件を満たす場合に特定のマーカーを返すことで、テストが通るかどうかを判断します。しかし、実際のテスト時間は8.8秒かかり、従来の方法に比べて非常に遅く、実用性に疑問が残ると指摘されています。 • AI Claude Code SDKを使用して自然言語によるアサーションを行う方法を提案 • `assertAI`関数を用いて、特定のプロンプトに基づくAIの応答を確認する • AIが条件を満たす場合に特定のマーカーを返す仕組み • テストの実行時間が8.8秒かかり、従来の方法に比べて遅い • 実用性に疑問が残るため、AIによるルールベースの書き換えが必要とされる
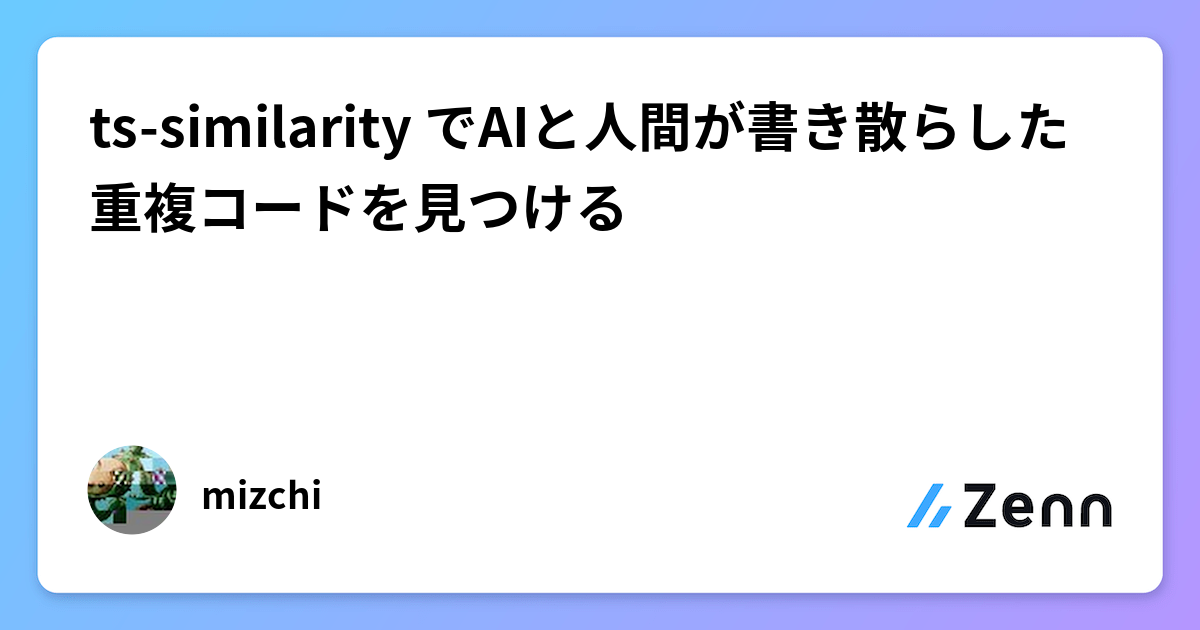
この記事では、Rustで実装されたts-similarityというツールを紹介しています。このツールは、TypeScriptで書かれたコードの中からAIと人間が書いた重複コードを検出するためのもので、AST(抽象構文木)を基にした構造比較を行います。主に関数の比較に焦点を当てており、ブルームフィルタやマルチスレッド処理を用いて効率的に重複を検出します。実際の使用例として、複数のファイルを分析し、重複する関数ペアを特定する様子が示されています。また、今後の機能追加として、型定義リテラルの重複検知やコード品質の測定などが挙げられています。 • AIと人間が書いた重複コードを検出するツールの開発 • ASTを基にした構造比較で関数の類似度を検出 • ブルームフィルタによる事前フィルタリングで効率化 • マルチスレッド処理を導入し、処理速度を向上 • 今後の機能追加として型定義リテラルの重複検知やコード品質の測定を計画
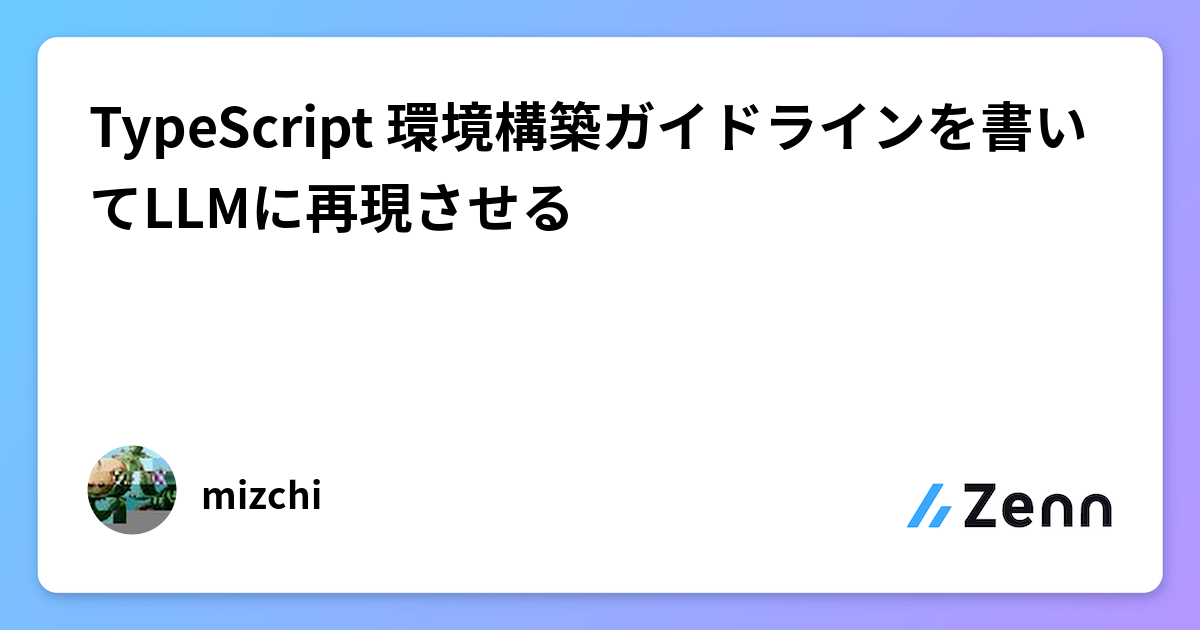
この記事では、TypeScriptの環境構築ガイドラインを作成し、LLM(Claude)に再現させる方法について説明しています。TypeScriptのツールチェインは多様で、プロジェクト設定が難しいため、再現性のある手順を作成しました。具体的には、プロジェクトの要件をLLMに伝え、適切な設定を追加させる方法を示しています。手順書には、不要なドキュメントを削除する指示も含まれており、AIが混乱しないよう配慮されています。また、各ツールの選択理由や設計思想も明確に記述されています。今後は、LLMが進化することで、ガイドライン自体も自動更新される可能性があると述べています。 • TypeScriptプロジェクトの環境構築が難しい問題を解決するためのガイドラインを作成した。 • LLMにプロジェクトの要件を伝え、適切な設定を追加させる手法を提案している。 • 手順書には不要なドキュメントを削除する指示が含まれており、AIの混乱を防ぐ工夫がされている。 • 各ツールの選択理由や設計思想を明確に記述し、後からの拡張を重視している。 • 今後、LLMの進化によりガイドラインが自動更新される可能性がある。
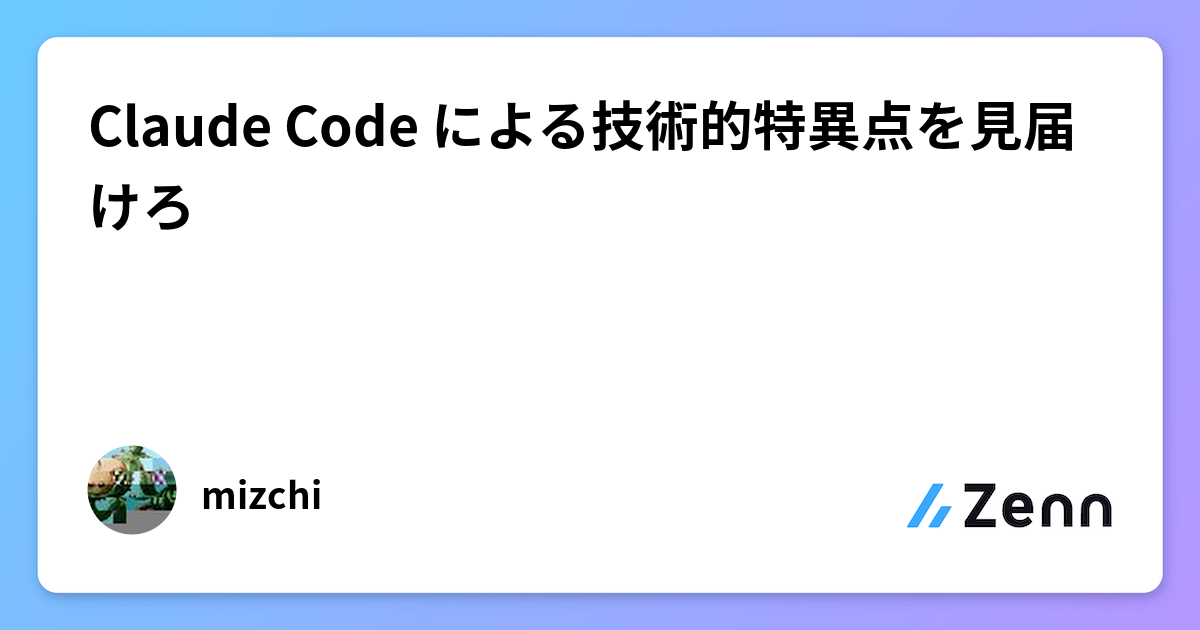
この記事では、AI Claude Codeの進化とその影響について論じられています。著者は、Claude Codeが自己改善を通じてソフトウェア開発における知識爆発を引き起こす可能性があると述べています。特に、Claude Codeは自身の開発の90%を自ら行っており、これによりエージェントとモデルの相互作用が進化しています。著者は、AIの自己改善が技術的特異点に近づく可能性があると考え、Claude Codeの機能追加の速さや、ユーザーからのフィードバックを自動的に取り入れる仕組みについても触れています。最終的に、Claude CodeがAI2027で予言されている自己改善AIの実現に寄与する可能性があると結論づけています。 • Claude Codeは自己改善を通じてソフトウェア開発における知識爆発を引き起こす可能性がある。 • Claude Codeの90%は自ら開発されており、エージェントとモデルの相互作用が進化している。 • AIの自己改善が技術的特異点に近づく可能性がある。 • Claude Codeはユーザーからのフィードバックを自動的に取り入れる仕組みを持っている。 • Claude Codeの機能追加の速さが注目されている。
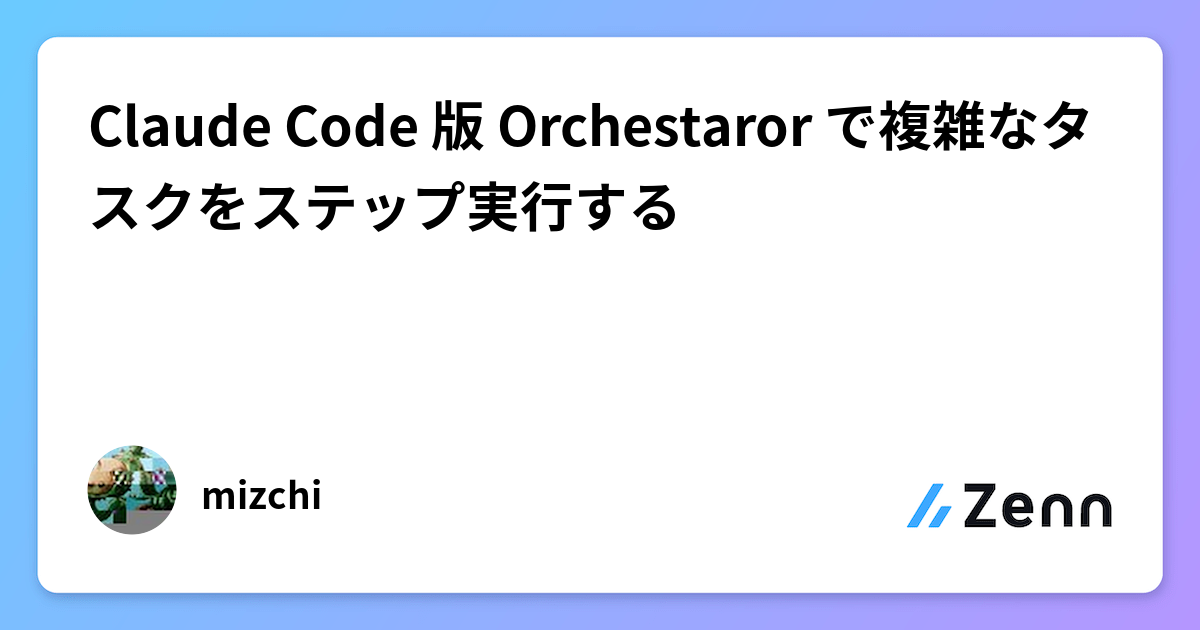
この記事では、Claude Codeを用いたOrchestratorの実装について説明しています。Roo OrchestratorのClaude版を作成し、複雑なタスクを段階的に分解して実行する方法を提案しています。具体的には、タスクを初期分析、ステップ計画、逐次実行、ステップレビュー、進行的集約の5つのプロセスに分け、各ステップで並列にサブタスクを実行します。この手法により、タスクのコストを削減し、効率的に処理することが可能です。また、各サブタスクから得られた結果を次のステップに活用することで、逐次的に理解を深めることができます。 • Roo OrchestratorのClaude版を作成し、複雑なタスクを効率的に分解・実行する手法を提案 • タスクを初期分析、ステップ計画、逐次実行、ステップレビュー、進行的集約の5つのプロセスに分ける • 各ステップで並列にサブタスクを実行し、タスクのコストを削減 • サブタスクから得られた結果を次のステップに活用し、逐次的に理解を深める • タスクの依存関係を明確にし、実行順序を計画することが重要
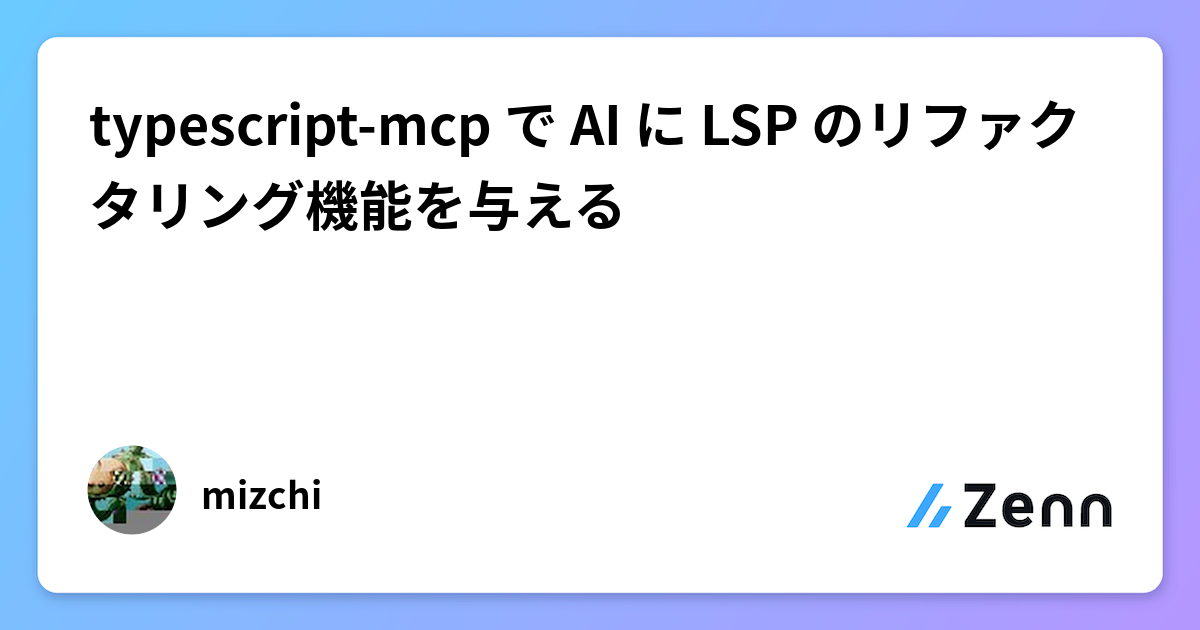
この記事では、TypeScript用のModel Context Protocol(MCP)を使用して、AIにLSP(Language Server Protocol)のリファクタリング機能を提供する方法について説明しています。まず、npmを使用して必要なパッケージをインストールし、MCPサーバーを立ち上げる手順が示されています。MCPサーバーは、ファイルの移動やシンボルのリネーム、参照の検索など、LSPの機能を提供します。具体的なコマンド例も挙げられ、TypeScriptプロジェクトの設定方法やMCPの使用方法が詳述されています。また、AIがコードを生成する際の課題や、MCPを使用することで得られる安全なリファクタリングの利点についても触れられています。 • TypeScript用のMCPを使用してAIにLSPのリファクタリング機能を提供する方法を解説 • npmで必要なパッケージをインストールし、MCPサーバーを立ち上げる手順を示す • MCPサーバーはファイル移動、シンボルリネーム、参照検索などのLSP機能を提供 • 具体的なコマンド例を挙げてTypeScriptプロジェクトの設定方法を説明 • AIによるコード生成の課題とMCPを使用することで得られる安全なリファクタリングの利点に言及
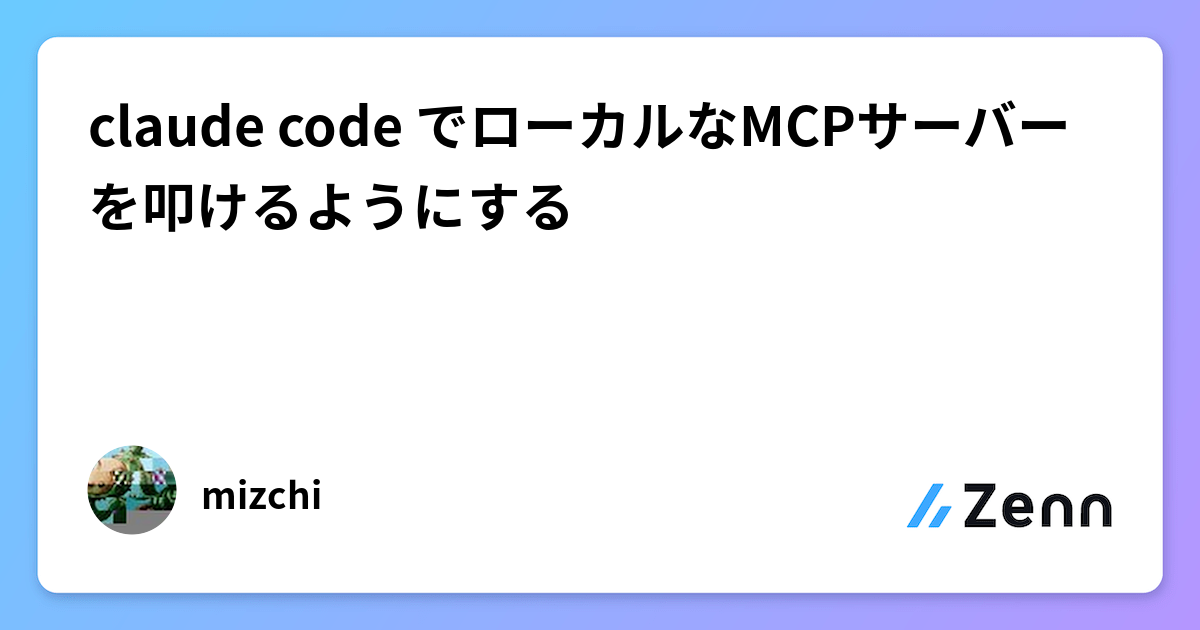
この記事では、Claude Codeを使用してローカルなMCP(Model Context Protocol)サーバーに接続する方法について説明しています。具体的には、`claude --mcp-config=...`コマンドを使用してローカルMCPサーバーを叩く手順が示されています。プロジェクトルートにある`.mcp.json`ファイルが自動的に認識され、MCPサーバーの実装例として、指定したURLから本文を抽出しMarkdown形式で返す機能が紹介されています。また、Deno環境でのMCPサーバーの起動方法や、Node互換モードでの実装についても触れられています。 • ローカルMCPサーバーに接続するための具体的なコマンドと設定方法が示されている。 • MCPサーバーの実装例として、URLから本文を抽出しMarkdown形式で返す機能が提供されている。 • Deno環境でのMCPサーバーの起動方法が説明されている。 • Node環境でも同様の実装が可能であることが示されている。 • 標準入出力でのサーバー接続方法が具体的に記載されている。
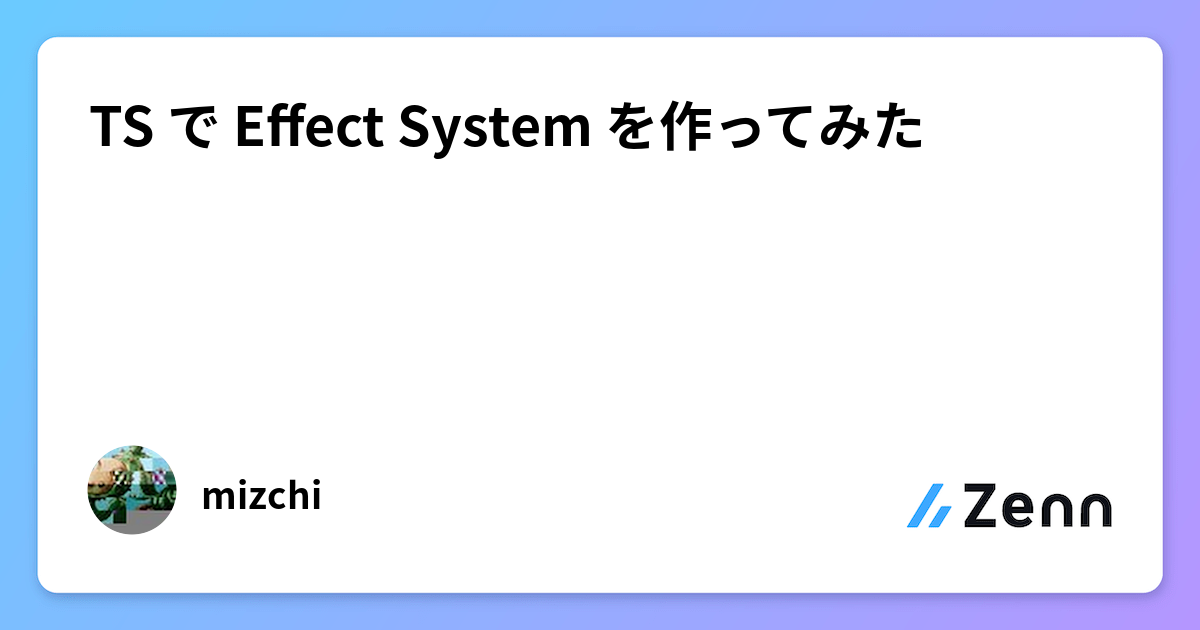
この記事では、TypeScriptを用いてEffect Systemを実装する方法について説明しています。Effect Systemは、プログラムの実行をAsyncGeneratorまたはGeneratorのイテレータで表現し、エフェクトの宣言とそれに対応するハンドラを注入する仕組みを持っています。具体的には、エフェクトを定義し、プログラム内でそれを使用することで、型による副作用の記述を強制し、実行時にハンドラの同期/非同期を決定することができます。また、プログラムを分割してテストする際の利点や、内部トレーサビリティを持つテストの書き方についても触れています。 • TypeScriptでEffect Systemを実装する方法を解説 • プログラムの実行をAsyncGeneratorまたはGeneratorで表現 • エフェクトの宣言とハンドラの注入により型による副作用を強制 • 実行時にハンドラの同期/非同期を決定可能 • プログラムを分割して部分的にテストできる利点 • 内部トレーサビリティを持つテストが可能
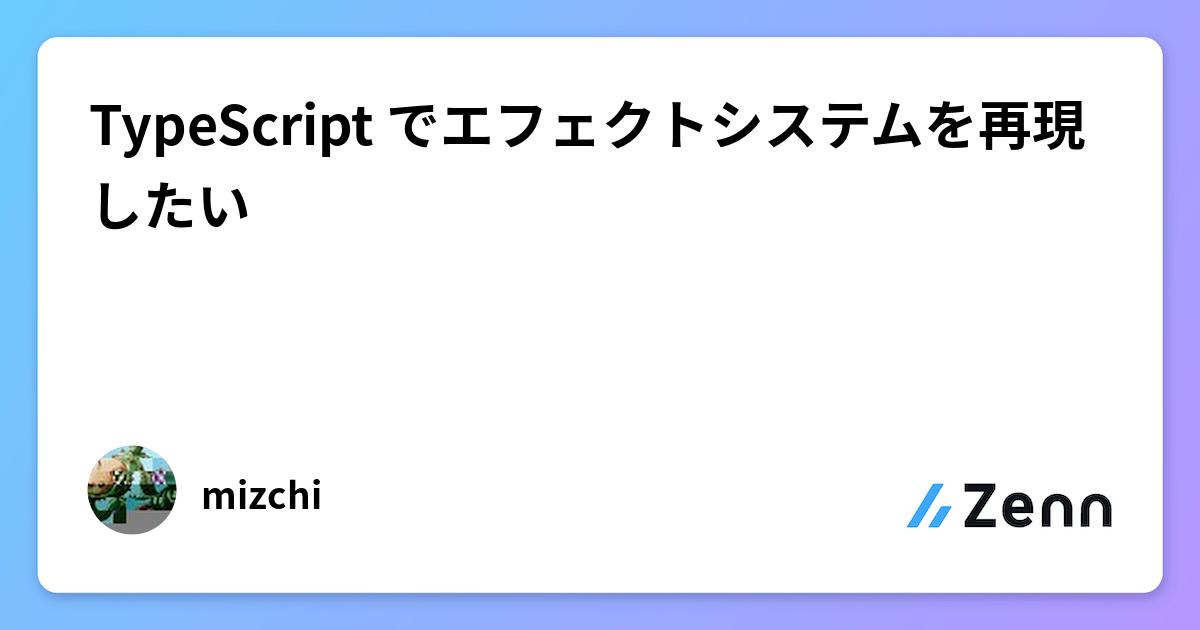
この記事では、TypeScriptを用いてエフェクトシステムを再現する方法について解説しています。著者は、TypeScriptの言語システムが副作用を持つ関数の型を表現するのに限界があると感じ、Async Generatorを利用して副作用の型を宣言する手法を試みました。具体的には、関数に副作用のシグネチャを付与し、代数的データ型を用いて実装と副作用を分離することに重点を置いています。最終的に、Generatorを使用して副作用を持つプログラムを構築し、共通のハンドラーを通じて処理を行う方法を示しています。記事では、具体的なコード例を交えながら、Generatorの使い方やハンドラーの定義方法についても詳しく説明しています。 • TypeScriptのエフェクトシステムの再現に関する技術的な解説 • 副作用を持つ関数の型を表現するためのAsync Generatorの利用 • 代数的データ型を用いた実装と副作用の分離 • Generatorを使用した副作用を持つプログラムの構築方法 • 共通のハンドラーを通じて処理を行う手法の紹介
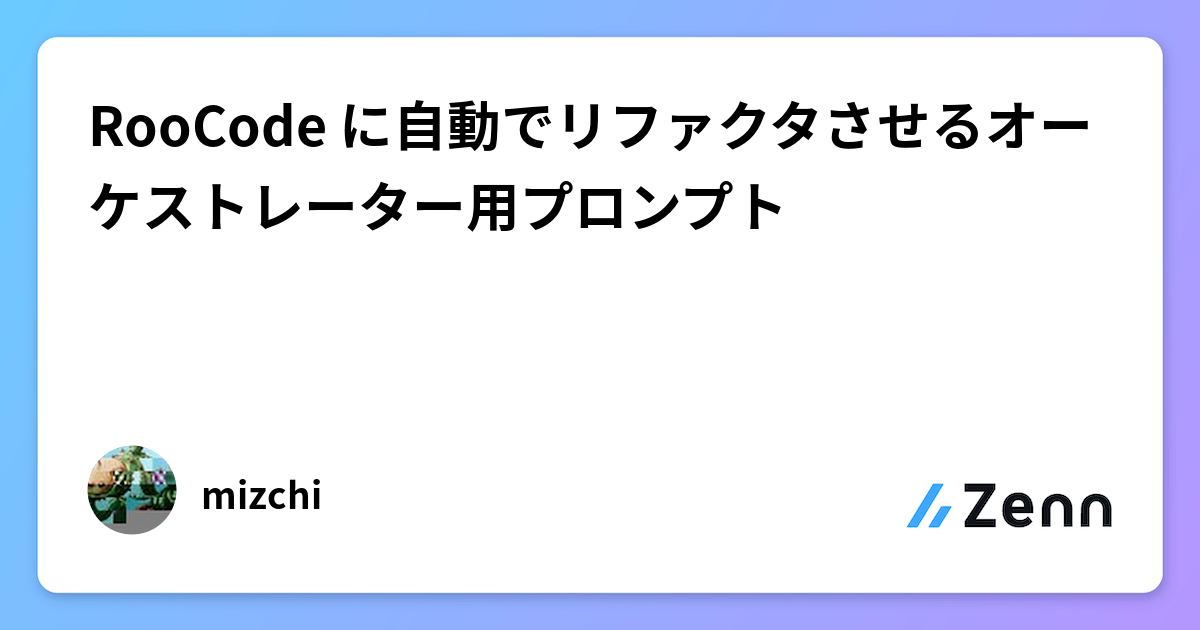
この記事では、RooCodeを用いたオーケストレーター用プロンプトの自動リファクタリングについて説明しています。特に、Deno環境でClaude 4を活用し、リファクタリングのプロセスを改善するための新しいプロンプトが導入されました。リポジトリのリンクが提供されており、特に.rules.mdと01_workflows.mdのファイルが重要です。リファクタリングの際には、ハイラムの法則や単一責任原則を考慮し、ESLintの積極的なルールを適用しています。また、タスク分析やサブタスクの分割を行うことでコスト削減が実現され、特化したプロンプトが用意されています。新機能追加やAPI設計改善に焦点を当てたワークフローも定義されていますが、旧APIとの互換性に関する課題も指摘されています。 • RooCodeを用いたオーケストレーター用プロンプトの自動リファクタリングを実施 • Deno環境でClaude 4を活用し、リファクタリングプロセスを改善 • ハイラムの法則や単一責任原則を考慮したリファクタリング • ESLintの積極的なルールを適用し、デッドコードの削除を実現 • タスク分析やサブタスク分割によりコスト削減を達成 • 特化したプロンプトを用意し、新機能追加やAPI設計改善に焦点を当てたワークフローを定義 • 旧APIとの互換性に関する課題が存在
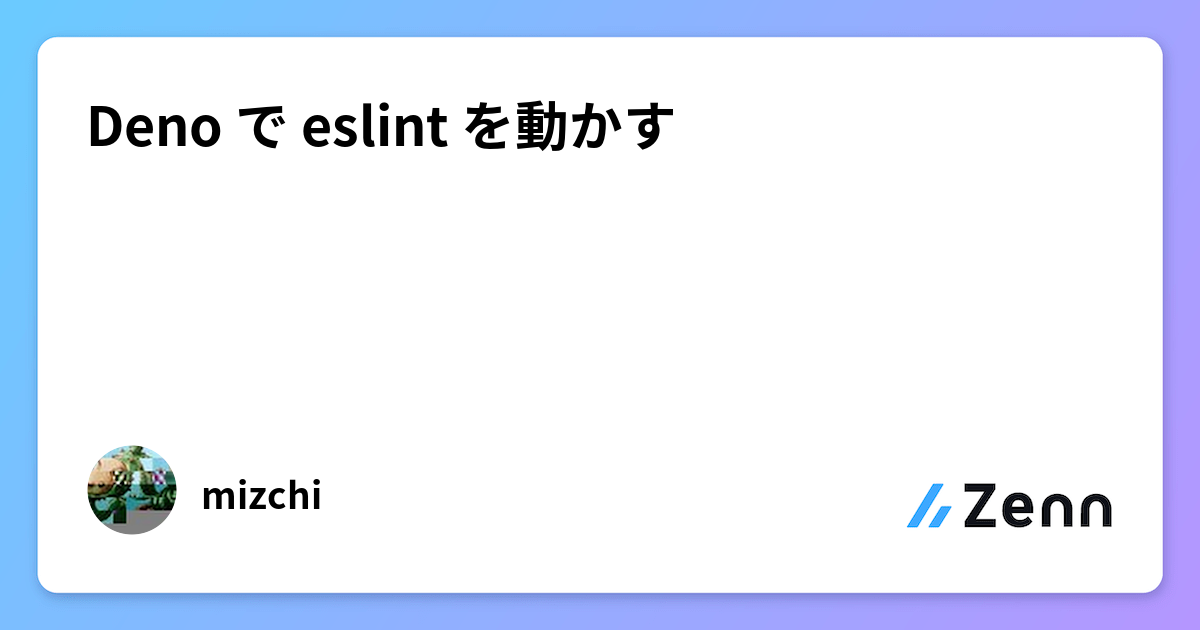
この記事では、Deno環境でESLintを動かす方法について説明しています。Denoの標準のlint機能ではルールが不足しているため、ESLintを使用することにしました。具体的には、DenoでESLintを実行するためのコマンドや設定ファイルの構成、Node互換モードでの依存関係の追加方法、カスタムルールの作成方法などが詳述されています。また、型チェックはDeno LSPがないため不整合が生じることが指摘されています。最終的に、ESLintを使って構文チェックを行うことができることが確認されました。 • Denoの標準lint機能ではルールが不足しているため、ESLintを使用する必要がある。 • DenoでESLintを動かすためのコマンドは「deno run -A npm:eslint」である。 • 型チェックはDeno LSPがないため、tseslint.configs.strictTypeCheckedは動作しない。 • Node互換モードで依存関係を追加する手順が示されている。 • カスタムルール「no-class」を作成し、クラスの使用を禁止することができる。 • ESLintを使って構文チェックを行うことができ、警告やエラーが表示される。 • 型の解決は自分で行う必要があり、deno-graphやLSPを利用することが可能。
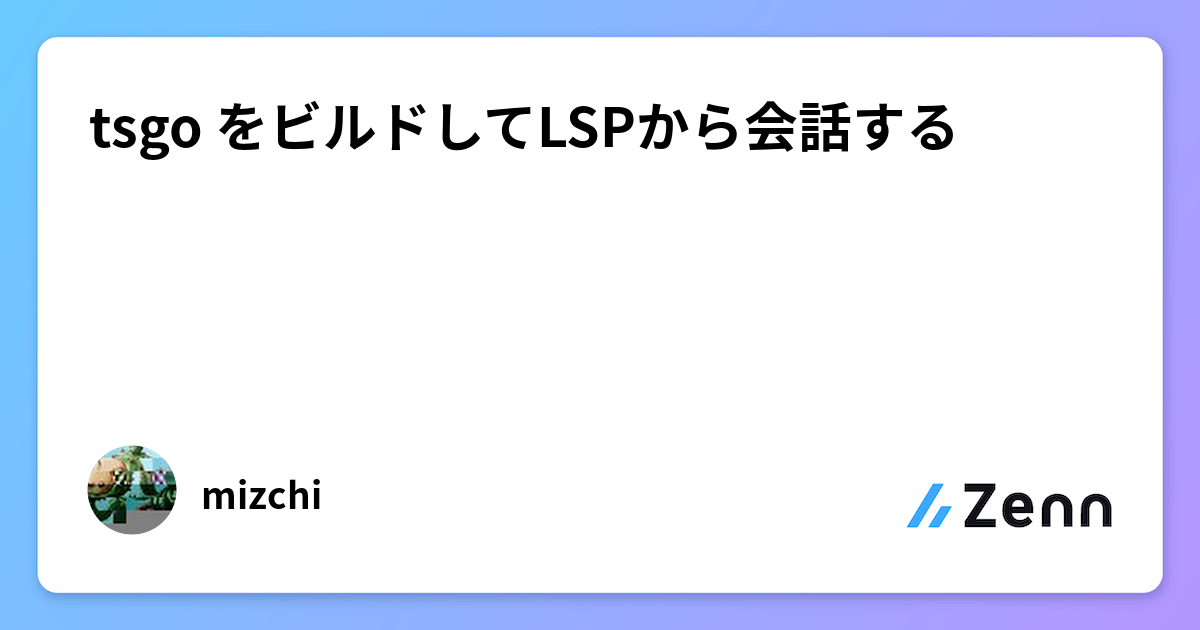
この記事では、TypeScriptのGo移植実装であるtsgoについて説明しています。tsgoの主な目的は、コンパイラの並列化であり、特にTypeCheckerの並列化に焦点を当てています。初期設定では、TypeCheckerを4つ作成し、ソースコードをシャーディングして解析結果を共有メモリに保存します。現在の進捗として、parserとscannerの手作業での移植が完了し、ASTの変換が進められています。また、LSPの実装に関しては、LanguageServiceを移植せず、IPCによるAPI層を構築中です。zodライブラリを使用した型推論の例も示されており、tsgoコマンドを使用してTypeScriptの型チェックを行う方法が説明されています。 • tsgoの主な目的はコンパイラの並列化で、特にTypeCheckerの並列化に焦点を当てている。 • 初期設定ではTypeCheckerを4つ作成し、ソースコードをシャーディングして解析結果を共有メモリに保存する。 • parserとscannerの手作業での移植が完了し、ASTの変換が進められている。 • LSPの実装ではLanguageServiceを移植せず、IPCによるAPI層を構築中である。 • zodライブラリを使用した型推論の例が示されており、tsgoコマンドを使用してTypeScriptの型チェックを行う方法が説明されている。
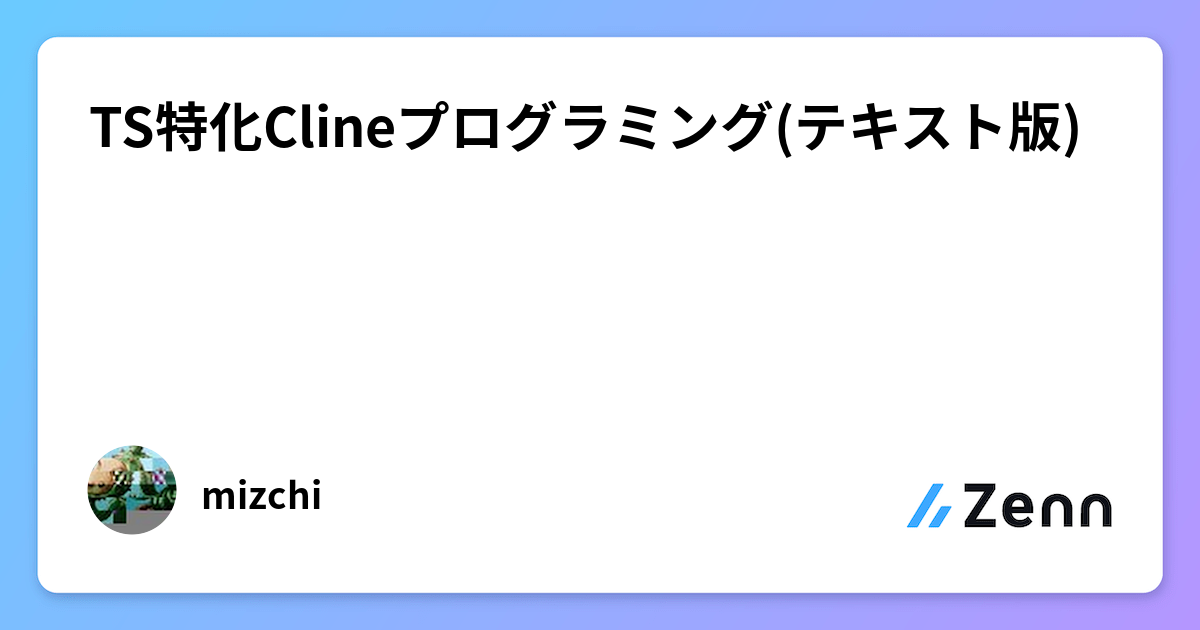
この記事は、TypeScriptに特化したClineプログラミングに関する内容を扱っており、特にプロンプトの作成に関するベストプラクティスを紹介しています。具体的には、効果的なプロンプトの書き方や、テスト駆動開発(TDD)の重要性、自己修復能力を持つコードの生成方法について述べています。また、ファイル配置規則やドメイン型の集約方法、関数型ドメインモデリングの実践例も示されています。さらに、テストカバレッジの向上を目指すための自動生成テストの手法や、ライブラリの置き換えに関する具体的なプロンプトの例も提供されています。全体として、TypeScriptを用いたプログラミングにおける効率的な手法とその実装方法が詳述されています。 • TypeScriptに特化したプロンプト作成のベストプラクティスを紹介 • テスト駆動開発(TDD)の重要性を強調 • 自己修復能力を持つコード生成の方法を提案 • ファイル配置規則やドメイン型の集約方法を示す • テストカバレッジ向上のための自動生成テスト手法を紹介 • ライブラリの置き換えに関する具体的なプロンプトの例を提供

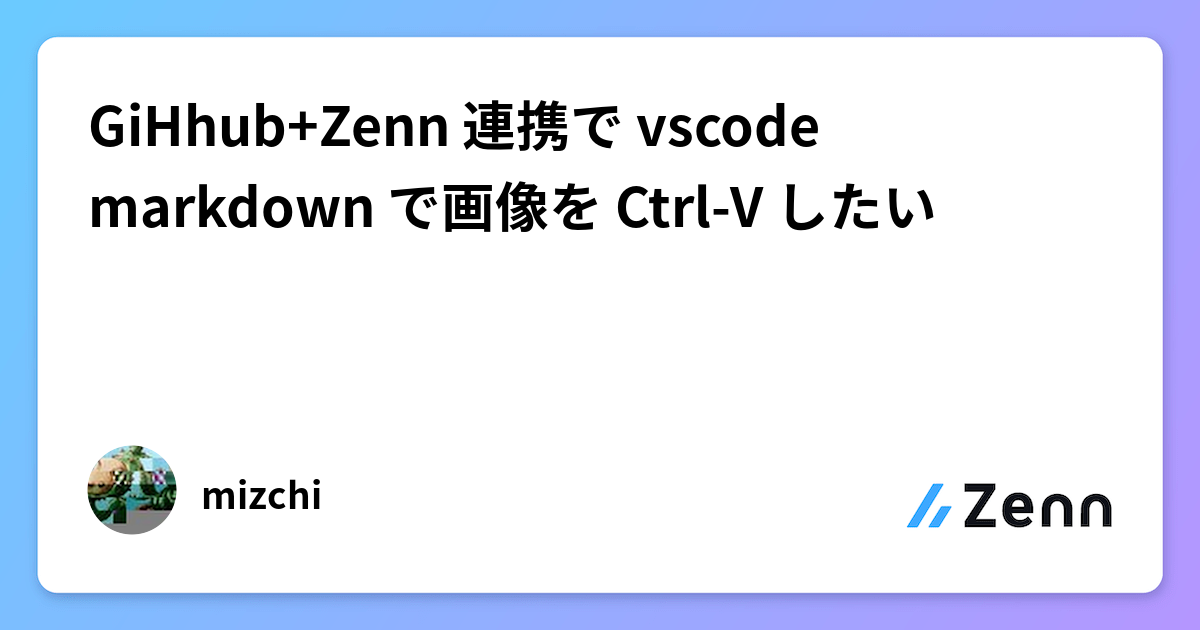


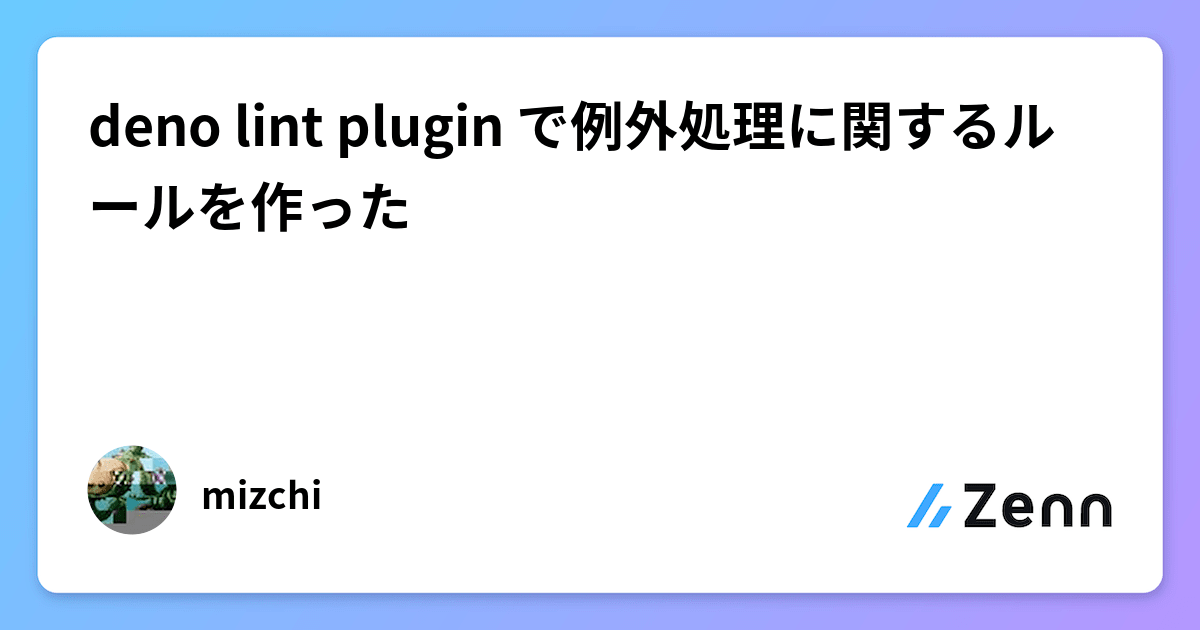

前半は手元で動かしながら要点を掴み、後半は概念を掴んで何ができるかを知ることを目的とします。